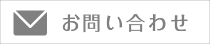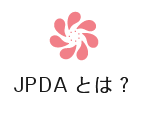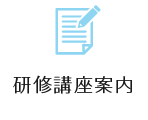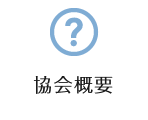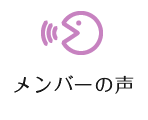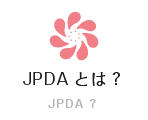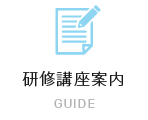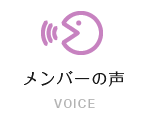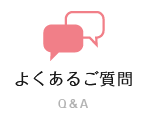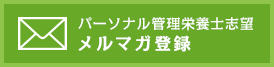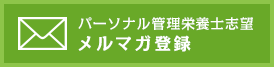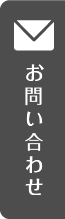メンタルヘルスを整える食事のヒント|ストレスに効く栄養素4選/香取美江
前回のコラムでは、ストレスフルな管理職が健康を維持するための食生活のポイントとして、健康を最優先に考えるマインドセットの重要性や、バランスの取れた食事の組み合わせ、食事のタイミングについてお伝えしました。
今回は、メンタルヘルスと食事の関係性について探っていきます。
2025年4月23日
今回は、メンタルヘルスと食事の関係性について探っていきます。
ストレスと身体の関係性
●ストレス太りの原因はホルモンにあった!コルチゾールと食欲のメカニズム
ストレスがかかると、体内で「コルチゾール」というホルモンが分泌されます。この「コルチゾール」はストレスから身を守るために分泌されますが、血糖値を上げる役割があります。
上がった血糖値を下げるために、「インスリン」というホルモンが分泌され血糖値が下がります。
この際に、食欲が増すことがあり、特に甘いものや高カロリーな食べ物を欲する傾向が強まります。この現象は、「ストレス食い」や「ストレス太り」の原因となります。甘いものやジャンクフードを摂取すると、一時的に気分が良くなることがありますが、実際には血糖値が急激に上昇し、その後急降下することで、体調が不安定になり、さらなるストレスを招く悪循環が生まれます。
上がった血糖値を下げるために、「インスリン」というホルモンが分泌され血糖値が下がります。
この際に、食欲が増すことがあり、特に甘いものや高カロリーな食べ物を欲する傾向が強まります。この現象は、「ストレス食い」や「ストレス太り」の原因となります。甘いものやジャンクフードを摂取すると、一時的に気分が良くなることがありますが、実際には血糖値が急激に上昇し、その後急降下することで、体調が不安定になり、さらなるストレスを招く悪循環が生まれます。
●ストレスで栄養が消耗?疲れやすくなる原因と対策栄養素
ストレスを感じていると、体は通常よりも多くの栄養素を消費します。特に、ストレスにより、たんぱく質、ビタミンB群、ビタミンCが多く消費されます。これらの栄養素は、健康をサポートしたり、ストレスに対抗する役割を果たします。
たんぱく質はホルモンの材料になり、ビタミンB群は神経伝達物質の生成に関与し、ビタミンCは免疫機能をサポートします。そのため、ストレスを感じると、これらの栄養素が不足しがちになます。その結果、心身ともに疲れやすくなり、集中力の低下やイライラするなど、仕事の効率にも影響が出る可能性があります。これを防ぐためには、ストレスを感じた際に、これらの栄養素を意識して摂取することが重要です。
たんぱく質はホルモンの材料になり、ビタミンB群は神経伝達物質の生成に関与し、ビタミンCは免疫機能をサポートします。そのため、ストレスを感じると、これらの栄養素が不足しがちになます。その結果、心身ともに疲れやすくなり、集中力の低下やイライラするなど、仕事の効率にも影響が出る可能性があります。これを防ぐためには、ストレスを感じた際に、これらの栄養素を意識して摂取することが重要です。
ストレスを軽減する栄養素4選
1.たんぱく質
ストレスを感じているときに、消費しがちなたんぱく質を摂取することが効果的です。ストレスへの耐性を高める助けとなります。
▶おすすめ食材:鶏肉、魚、卵、大豆製品(豆腐や納豆など)
2.ビタミンB群
ビタミンB群は、神経伝達物質の生成に関わる栄養素です。特にビタミンB6は、喜びや意欲をもたらす「ドーパミン」、落ち着きや安定感をもたらす「セロトニン」というホルモンの生成過程で、なくてはならない栄養素です。また、ビタミンB1は「疲労回復」のビタミンとも呼ばれており、神経や筋肉の機能を正常に保つ効果があるとされています。
▶おすすめ食材:B6・・・レバーやさんま、B1・・・赤身肉や大豆製品
3,ビタミンC
ビタミンCは「コルチゾール」の材料のひとつであり、ストレスにより「コルチゾール」の分泌が増えるとビタミンCが必要以上に消費されてしまいます。
▶おすすめ食材:フレッシュな野菜、果物
4.マグネシウム
マグネシウムは「セロトニン」の分泌を促すために必要な栄養素です。ストレスによって尿からの排出が多くなるといわれています。
▶おすすめ食材:豆類、種子類(ナッツ、ごまなど)、海藻類
まとめ
ストレスと食事は密接に関係しています。食事を見直すことでストレスへの耐性を高め、仕事のパフォーマンスを向上させることができます。忙しい管理職の方々には、ストレスに強い体を作るために、栄養バランスの良い食事と適切な食生活のタイミングを意識することが重要です。
小さな工夫を積み重ねることで、より健全な体と心を維持し、日々の仕事に活かすことができるでしょう。
執筆管理栄養士:香取美江
小さな工夫を積み重ねることで、より健全な体と心を維持し、日々の仕事に活かすことができるでしょう。
執筆管理栄養士:香取美江
参考文献
- 「日本人の食事摂取基準」,厚生労働省(2025年)
- 「職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」,厚生労働省,(2025年3月17日閲覧)
- 功刀浩「こころに効く精神栄養学」女子栄養大学出版(2016年)
- 樺沢紫苑「精神科医が教える ストレスフリー超大全-人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をなくすためのリスト」ダイヤモンド社(2020年)